
(『近江聖人 中江藤樹』
http://www.biwa.ne.jp/~adogawa/nakaetouzyu/nakae-index.htm )
/小学校/道徳/高学年/
中 江 藤 樹
小林 義典 【TOSS SANJO】
江戸時代初期の儒学者で,日本における陽明学の開祖。
数多くの徳行・感化によって,没後も〈近江聖人〉として敬われ慕われている。
「人間は本来誰もが美しい心を備えている」ということを説き続けた中江藤樹。
藤樹の心を少しでも子供たちに伝えたいと願い,授業プランを作った。
| 【説明1】江戸時代の初め頃のお話です。400年くらい前に近江国(今の滋賀県)で実際にあったお話です。
(地図帳で滋賀県を見つけましょう。見つけた人は見つけましたと言いましょう。) 近江国に馬子の又左衞門という人がいました。馬に人や荷物をのせて運ぶ仕事をする人を馬子と言いました。 ある日,馬子の又左衞門は京都へ向かう飛脚を馬に乗せました。 当時,手紙などを遠くへ届ける仕事をする人を飛脚といいました。 馬子の又左衞門は飛脚を終えて家にもどり,馬を洗おうと鞍を取り外しました。そうしたら,さいふのような袋が出てきました。 その中味を改めると,なんと200両もの大金が入っているのでした。 驚いた馬子は, 「これはもしかしたら,さっきの飛脚のものかも知れない。 今ごろは,あの飛脚きっと困り果てているに違いない」 と思いました。 そして,ふたたび馬子は日暮れの道を,飛脚の泊まっている宿まで,30キロの道のりを走っていったのです。 いっぽう,飛脚はというと,宿で旅の疲れをいやそうとしたところ,大金の入った袋が手元にないことにようやく気づきました。 そして,必死であたりを捜したものの,どこにも見つかりませんでした。 そうした折,馬子が宿に現われました。 そして,馬子は200両の入った袋をそっくりそのまま返してあげました。飛脚は, 「この金子は藩の公金で,京の屋敷へ送り届けるためのものです。 もしも,この金子200両が見つからなかったときは,自分は死刑になったでしょう。 親兄弟までも重い罪になるところでした」 と,涙を流しながら話しました。 そこで飛脚は,荷物の中より財布を取り出し,とりあえずのお礼として馬子に15両を差し上げようとしました。 しかし,馬子は一向にそれを受け取ろうとはしませんでした。 |
| 【発問1】さて,馬子はなぜ受け取らなかったのでしょうか。 |
・お金をもらっただけじゃあ,全然嬉しくないと思ったからです。
・当たり前のことをしただけだからです。
・人が死刑になると困るからです。
・同じ人間として当たり前のことだからです。
・当たり前のことをしただけだからお金はいらないと思った。
| 【説明2】馬子は「そなたの金を,そなたに返したただけなのに,なんでお礼などいりましょうや」と言うばかりでした。 しかし,飛脚はお礼をしなければ気が済みませんでした。そこで,飛脚は15両を10両に減らしました。 それでも馬子の又左衞門は受け取りません。 さらに5両,3両と減らして馬子に受け取ってもらおうとするのですが,それも受け取ろうとはしませんでした。 しかし,困りはてた飛脚の顔を見かねて,ようやく馬子は「それじゃ,ここまで歩いてきた駄賃として200文だけは頂戴いたしましょう」と言いました。 |
| 【発問2】さて,馬子はこの200文をどうしたと思いますか。 |
・馬を買ったと思います。
・馬の鞍を新しく買ったと思います。
| 【説明3】 200文を受け取った馬子は,その金で酒を買ってきました。そして,宿の人たちと楽しそうに一緒に酒を飲み交わし始めました。 酒もなくなり,馬子がほろ酔い機嫌で帰ろうとしました。その時,飛脚は感激のあまり馬子に聞きました。 「あなたはどのような方ですか」と問うたのです。 |
| 【発問3】さて,飛脚は馬子のどんなところに感激したのですか。 |
・お金をもらっても,自分だけのものにしなかったところです。
・自分がもらったお金なのに,お酒を買ってみんなで分けたところに感激したと思います。
| 【説明4】 馬子は,次のように答えました。 「自分は名もない馬子に過ぎません。 ただ,自分の家の近所に小川村(現在の滋賀県安曇川町上小川)というところがあって, この村に住んでおられる中江藤樹という先生が,毎晩のようにお話をしてくださり,自分も時々は聞きにいくのです。 先生は,親には孝を尽くすこと,(親孝行のことです。親の言いつけをよく守り,老後には面倒を見ることです。) 人の物を盗んではならないこと,人を傷つけたり,人に迷惑をかけたりしてはならないことなど, いつも話されておられます。今日のお金も,自分の物ではないので,取るべき理由がないと思ったまでのことです。」 そう言って,夜も遅いのに自分の家に向かって歩き始めました。 |
| 【発問4】このお話を聞いて,どう思いましたか。 【指示1】ノートに書きなさい。 |
| (子供がノートに感想を書いている間に,次のように板書する。) 中江藤樹(近江国小川村)のお話 一 親に孝を尽くす(親孝行をする) 二 人の物を盗んではならない 三 人を傷つけたり,人に迷惑をかけたりしてはならない など |
・馬子はいい人だと思いました。悪い人だったら200両は盗んでいるからです。
あと,中江藤樹という人の言いつけを守っていたからです。
・馬子は中江藤樹という人に,いいことを教えてもらっているだけではなく,自分もそのことを実行しているから
すごくいい人だと思います。
・中江藤樹さんは馬子にいろいろないい話とかをしてくれていい人だと思う。
・馬子は,もらったお金でお酒を買ってみんなで分けて,自分だけで飲まないでみんなで飲んで,優しい人だなと思いました。
・馬子はすごく親切だと思いました。理由は,お金を落とした人にわざわざ届けにいってお金を渡したからです。
・私は,馬子はいい人だと思います。理由は,30kmも走って届けに行ったのに,その落としたお金の持ち主がくれたお金を少しになってからもらったからです。
・私なら最初から高いお金のままもらうけど,200文だけもらったからいい人だと思った。
・お金(金額)が少なくなってからやっともらって,みんなでお酒を飲んだからいい人だと思いました。
 |
【説明5】中江藤樹先生の肖像画を見せます。 (『近江聖人 中江藤樹』 http://www.biwa.ne.jp/~adogawa/nakaetouzyu/nakae-index.htm ) |
| 【説明6】中江藤樹先生は近江国小川村に生まれました。 9歳のときお母様のもとから離れ,おじいさまに預けられました。 その時から文字の読み書きを習い始めました。1年ほどで大変難しい本も読めるようになったと言われています。 10歳の時,伊予国大洲(愛媛県大洲市)へ移り住みます。 (地図帳で愛媛県を見つけます。見つけた人は見つけましたと言いましょう。) そこで自分の力で多くの本を読み,どんどんと学びを深めました。15歳で武士となり独り立ちしました。 しかし,28歳の時,武士の位をなげうって故郷の小川村へ帰りました。 |
| 【発問5】なぜ武士をやめて故郷へ帰ったのだと思いますか。 |
・故郷が見たくなったんだと思います。
・武士になっても独りぼっちだから故郷へ帰りたくなったんだと思います。
・お母さんが心配になったから。
| 【説明7】 中江藤樹先生の故郷の小川村にはお母様が年老いて独りで住んでいたんです。 中江先生は親孝行をするように人に教えていました。でも,自分が親孝行をしていないということですごく悩んだんです。 それで,周りの反対を押し切って無理やり故郷に帰りました。 当時,住む土地を勝手に変えることは許されることではありませんでした。親孝行をするために命懸けで故郷へ帰ったのです。 |
| 【説明8】 さて,中江藤樹先生のお母様については一つエピソードがあります。 中江藤樹先生が9歳の時,おじいさまに預けられました。9歳の時,お母様と離ればなれになりました。 お母様は病気がちで身体が弱かったので,離れて暮らすようになって心配でたまりませんでした。 そこで,学校を抜け出してお母様のお見舞いに行きました。 お母様は井戸の水を汲んでいるところでした。重いつるべを引っ張っているところでした。 9歳だった中江藤樹先生は「お母様!」と言って泣きながら走り寄りました。 ところが,藤樹先生のお母様は「止まりなさい」と言って藤樹先生が走り寄ってくるのを止めました。 そして,こう言ったのです。 「男の子は一度目標をもって家を出たら,めったな事で戻ってきてはなりません。私のことなど心配せずに学校にもどりなさい。」 こうピシッと言ったのです。 |
| 【発問6】みなさん,藤樹先生のお母様をどう思いますか。 |
・お母さんは本当は悲しいと思います。
・お母さんも本当は会えて嬉しいと思っているんだけど,厳しくしたんだと思います。
| 【説明9】 さて,28歳で故郷へ戻った中江藤樹先生は,自分の家で塾を開きました。 そして,自分の学んできたことを村の多くの人々に伝えました。
|
| 【発問7】「致良知」とはどういう意味だと思いますか。 |
・「正しいことを知る」ことだと思います。
・「正しいことを身に付ける」ことです。
| 「人は本来美しい心を備えている」(と板書する) |
| 【説明10】「人は本来美しい心を備えている」という意味です。 人や自分の善い面を引き出す生活をすることの大切さを伝えています。 自分が善いと信じたことを断固として実行する藤樹先生だからこそ, 村の人々は「致良知」という言葉を信じて努力したのだと思います。 馬子の又左衞門も,その中の一人ですね。 |
| 【説明11】 この時間に気づいたこと,分かったこと,思ったことなど 何でもいいですからノートに書きましょう。 書き終わったら先生に見せてください。 |
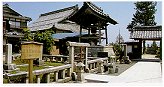 〈玉林寺〉 41歳でその生涯を閉じた 中江藤樹は,母堂,三男 と共に玉林寺の門前に眠 っています。 |
【説明12】 (ノートに書き始めてから30秒後くらいに) 中江藤樹先生が亡くなって何年もたってからのお話です。 一人の武士が小川村の近くを通るついでに,藤樹先生の墓を訪ねようと思いました。 畑を耕している農夫がいたので,その武士は農夫に道を聞きました。 農夫は自分が案内しようと言って先に立って歩いてくれました。 ところが,途中で農夫は自分の家に立ち寄って着物を着替え,羽織まで着て出てきました。 武士は心の中で,「自分を敬ってこのようにしたのだろう。」と思っていました。 藤樹先生の墓に着いた時,農夫は垣の戸を開けて,武士をその中に入らせ, 自分は戸の外にひざまずいて拝みました。 武士はそこで初めて,先程農夫が着物を着替えたのは藤樹先生を 敬うためであったと気が付きました。 それで深く感心して,ていねいに藤樹先生のお墓を拝んだということです。 |
| 【説明13】もう一つ,興味深いお話があります。 「致良知」に関する中江藤樹先生のお弟子さんのお話です。 親の土地を誰がどれだけ譲り受けるかということで,ある兄弟が激しくげんかをしていました。 代官がけんかをやめるよう命令しても全然聞きませんでした。 そこで,中江藤樹先生のお弟子さんがこの兄弟を仲直りさせるよう頼まれました。 お弟子さんはまずその兄弟を自分の家に呼びました。兄弟は小さな部屋に通されました。 お弟子さんは自分の家来に次のように言わせました。 「主人は急な用事が出来たので,しばらくお待ちください。食事とお風呂は自由に使っても構いません。」 しかし,藤樹先生のお弟子さんはその兄弟をずっと待たせておきました。 兄弟は憎しみ合っているので,最初何も話しませんでした。 けれど,だんだんと幼い日一緒に遊んだ頃のことや両親に大切に育てられたことを思い出しました。 ついには兄弟涙を流して,お互いに自分が悪かったと謝りおいおいと泣きました。 そこへお弟子さんが部屋に入り,一言「本当に喜ばしいこと」と話すと,兄弟は仲良く家に戻りました。 まさに,「致良知:人は本来美しい心を備えている」ですね。 |
〈参考資料〉
◆『近江聖人 中江藤樹』 http://www.biwa.ne.jp/~adogawa/nakaetouzyu/index.html
◆『安曇川散策 近江先人探求』 http://www.biwa.ne.jp/~adogawa/kankou/sansaku/sansaku-oumiseizini.htm
◆『陽明学とは』 http://ww91.tiki.ne.jp/~matsu/youmeigaku.htm
(『松ちゃんのホームページ』 http://ww91.tiki.ne.jp/~matsu/index.htm より)
◆『中江藤樹からの伝言』 http://www.ne.jp/asahi/kojo/bunko/index1-56.html
(『興譲文庫』 http://www.ne.jp/asahi/kojo/bunko/index.html より)
◆(財)新教育者連盟『生命の教育』
◆文部省『尋常小學修身書 巻五』(ノーベル書房㈱複製版)